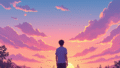生死を分けた「知識」の差 – 過去の災害から学ぶ
2011年3月11日、東日本大震災が発生した時、岩手県釜石市の小中学生たちは「津波てんでんこ」の教えに従い、より高い場所へと避難しました。
一方、「ここまで津波は来ない」と思い込んでいた地域では多くの犠牲者が出ました。
2018年の西日本豪雨でも同様に、ハザードマップの警告を真剣に受け止め早期避難した人々と、「自分は大丈夫」と思い込んだ人々の間に明暗が分かれました。
これらの事例が教えてくれるのは、災害時の生死を分けるのは、しばしば「知識」と「行動」の差だということです。
特に、自分の住む地域の災害リスクを正確に把握し、適切な避難行動をとれるかどうかが生存率を大きく左右します。
そこで重要な役割を果たすのが「ハザードマップ」です。
変わりゆく災害リスク – もはや「経験則」は通用しない

「この地域は昔から水害がない」「ここは安全だ」という経験則はもはや通用しなくなっています。
その理由は大きく二つあります。
一つは気候変動の影響です。近年の日本では「これまでに経験したことのない」豪雨や台風が頻発しています。
2019年の台風19号では、多くの河川が氾濫し、ハザードマップの想定を超える浸水被害が発生しました。
もう一つは都市開発の進行です。
森林の減少や地表のコンクリート化により、雨水の流れが変わり、これまで安全だった地域が新たな浸水リスクにさらされることがあります。
また、高層マンションの増加により、強風の通り道ができるなど、都市の災害リスクは刻々と変化しています。
こうした変化に対応するためには、最新のハザードマップで自分の住む地域のリスクを定期的に確認することが不可欠です。
ハザードマップで確認すべき災害別ポイント
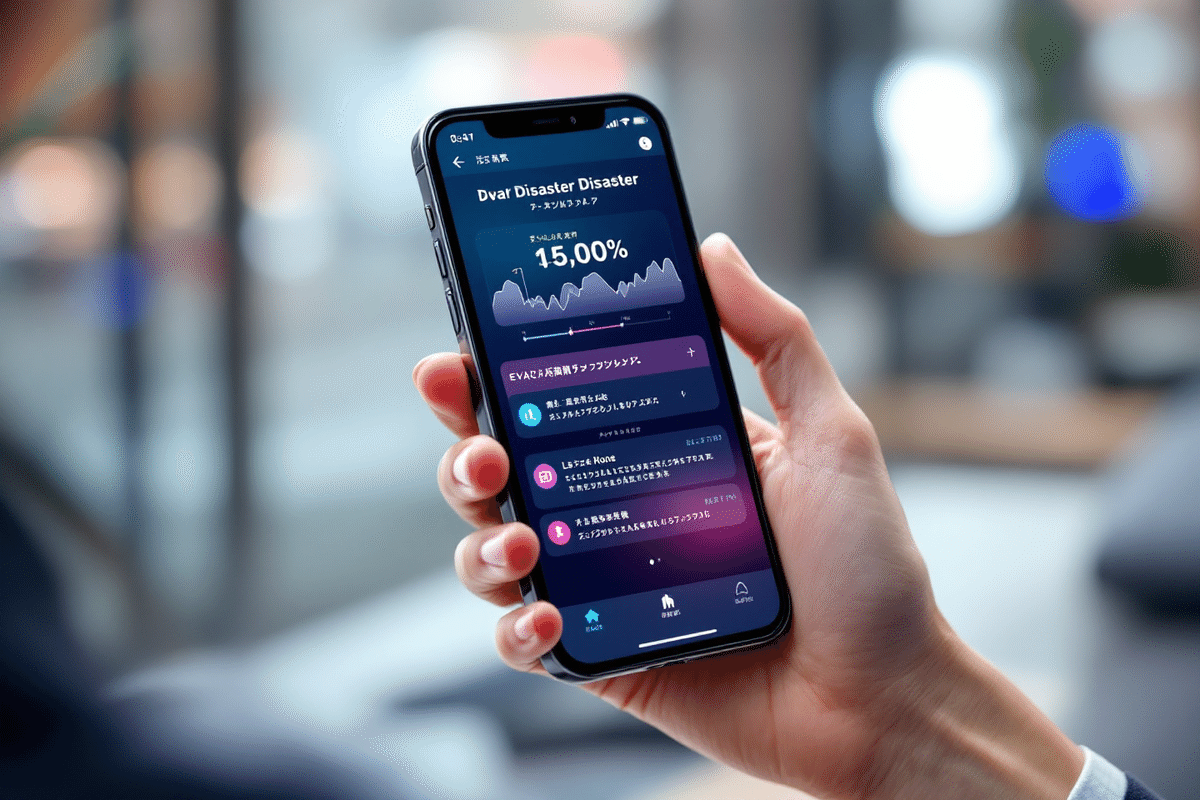
ハザードマップは災害の種類によって見るべきポイントが異なります。
洪水ハザードマップでは、浸水の深さと継続時間に注目しましょう。
浸水深が50cm以上になると歩行が困難になり、2m以上になると木造家屋が大きな被害を受ける可能性があります。
土砂災害ハザードマップでは、「土砂災害警戒区域」(イエローゾーン)と「土砂災害特別警戒区域」(レッドゾーン)の違いを理解することが重要です。
特にレッドゾーンは人命に関わる危険性が高い区域です。
地震ハザードマップでは、震度予測だけでなく、液状化リスクや建物倒壊リスクにも目を向けてください。
津波ハザードマップでは、浸水深だけでなく津波の到達時間も確認することが大切です。
到達時間が短い地域では、地震発生後すぐに高台への避難が必要です。
デジタル技術で進化する防災情報
現代のハザードマップはデジタル技術と融合し、より使いやすく、実用的になっています。
スマートフォンのアプリを使えば、現在地の災害リスクや最寄りの避難所をリアルタイムで確認できます。
「Yahoo!防災速報」や「NHK NEWS防災」などのアプリは、警報や避難指示の通知機能も備えています。
国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」では、複数の災害リスクを重ねて表示することができ、より総合的なリスク評価が可能です。
また、一部の自治体では、AR(拡張現実)技術を活用し、スマートフォンをかざすだけで浸水想定高を視覚的に確認できるサービスも始まっています。
こうしたデジタルツールを活用することで、より正確でタイムリーな防災情報を入手できるようになりました。
ぜひ日常的に活用してみてください。
知識を行動に変える時

東日本大震災や西日本豪雨の教訓は、「知っていること」と「行動すること」の間には大きな隔たりがあるということです。
ハザードマップで災害リスクを知ることは第一歩に過ぎません。
次に重要なのは、その知識に基づいて具体的な備えを行うことです。
避難場所や避難経路の確認、家族との連絡方法の取り決め、非常用持ち出し袋の準備など、今日からできる対策はたくさんあります。
ハザードマップが教えてくれる「次の一手」を、ぜひ実践してみてください。
災害はいつやってくるかわかりません。
しかし、適切な準備があれば、その被害を大きく軽減することができます。
ハザードマップを活用した詳しい防災対策については、完全版ガイドをぜひご参照ください。
あなたの行動が、大切な人の命を救うかもしれません。