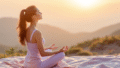楽しんでいた趣味が、実は防災の準備になる?
「週末のキャンプや登山が、実は防災の備えになっているとしたら?」
そんなふうに考えたことはあるでしょうか。
私たちが楽しみのために行っているアウトドア活動には、非常時に役立つスキルや知識がたくさん含まれています。
日本は地震や台風などの自然災害が多い国です。
どこで何が起きるか分からない今、無理なく備える方法として“趣味の延長線上の防災”という考え方が注目されています。
アウトドアで身につく力が、災害時に生きる
たとえばキャンプでは、火を起こしたり寝床を作ったり、限られた環境で食事をしたりと、自然の中で快適に過ごすための工夫が欠かせません。
これらの経験は、電気や水道が止まる災害時の状況にそのまま応用できます。
ヘッドライトで暗闇を照らす、テントやマットで寝床を作る、バーナーでお湯を沸かす──
これらはアウトドアでおなじみの行動ですが、実際の避難生活でも大きな助けとなります。
ふだんの道具が「もしも」の安心につながる
キャンプ用品は特別なものではありません。
多くはホームセンターや100円ショップで手に入り、普段の暮らしでも活用できます。
例えば、寝袋は避難所での寒さをしのぐ防寒具になりますし、広口の水筒は湯たんぽ代わりにもなります。
また、レトルト食品や缶詰なども、普段の食卓で使い慣れておくことで、非常時にも安心して食べられる「ローリングストック」が可能になります。
こうした“使い慣れておく”ことが、非常時のストレスを軽減します。
家族で学ぶ、防災の第一歩
子どもと一緒にキャンプや登山を楽しむことは、遊びながらサバイバル力を育てる絶好の機会です。
火のおこしかた、ロープの結び方、危険な場所の見分け方など、体験を通じて自然と身につけられることはたくさんあります。
親子でのアウトドア体験が、そのまま“もしも”への備えになるのです。
また、地域の災害リスクや避難場所を知っておく、家族で連絡手段を確認しておくことも、立派な備えの一つです。
防災は「やらなきゃ」ではなく「楽しみながら身につけるもの」
防災という言葉は、どこか義務的に聞こえるかもしれません。
でも、好きなことを通して自然と備えられるのなら、それは“暮らしの知恵”としてもっと身近に感じられるはずです。
次のアウトドアのとき、ちょっと視点を変えてみましょう。
「この道具、停電のときにも役立つかも?」「これがなかったらどうする?」
そんな問いかけから始めるだけで、日常が“備える力”に変わっていきます。