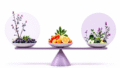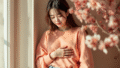「もし明日、電気も水道も止まったら?」
そんな非日常が、突然現実になるのが災害です。
けれど、実は私たちが日常で楽しんでいる“レジャーの知恵”が、非常時に大きな力になります。
その代表がキャンプをはじめとしたアウトドアの経験です。
日本は、美しい自然と引き換えに、地震・台風・集中豪雨などの災害リスクと常に隣り合わせの国です。
特別な防災訓練がなくても、レクリエーションの延長として、災害時に役立つ準備ができるとしたら
──それはとても心強いことです。
キャンプ道具が「防災道具」に変わる瞬間
キャンプ用品には、限られた環境下でも快適に過ごすための工夫が詰まっています。
例えば、テントやタープは、避難所でのプライベート空間の確保に有効です。
自宅の庭や公園での一時避難でも、安心して休む場所があるだけで、心の余裕が生まれます。
寝袋やコット(簡易ベッド)、厚手のマットは、地面からの冷えを防ぎ、体力を温存するうえでとても重要です。
非常時には、ぐっすり眠れるだけでも翌日の行動力が大きく変わります。
さらに、LEDランタンやヘッドライトといった照明器具は、停電時に欠かせません。
充電式や電池式のものを準備しておけば、夜間の移動や作業でも安心です。
「水」を制する者が、非常時を乗り越える
災害時に最も大切な資源のひとつが「水」です。断水が長引くと、飲み水だけでなく、手洗いや衛生管理にも困難が生じます。
登山やキャンプでは、自然の水を活用する知恵が身につきます。
携帯型の浄水器やろ過フィルターがあれば、川や雨水を飲用可能に変えることができます。
煮沸もまた有効な方法で、火器を使った水処理の経験があれば、限られた燃料でも効率よく安全な水を得ることが可能です。
加えて、日頃からペットボトルの水を多めに買い置きし、使った分だけ買い足していく「ローリングストック」も、無理なく備蓄を続けるコツです。
水は長期保存が可能な分、普段から意識しておくと安心です。
火を扱うスキルが“生きる力”になる
温かい食事は、災害時の心の支えにもなります。
小型バーナーや固形燃料を使えば、缶詰やアルファ米などを温めることができます。
アウトドア経験があれば、限られた水や燃料でも工夫して調理する知恵が自然と身につきます。
また、火の扱いに慣れていると、明かりや暖を取る手段としても応用が利きます。
ただし、室内や換気の悪い場所での火器使用には十分な注意が必要です。
安全な使い方を平常時から体得しておくことが大切です。
自然の中で鍛えられる“判断力と連携力”
アウトドアには、「状況に応じて判断する力」が求められます。天候の変化、体調の変化、道具の不具合──想定外のトラブルをどう乗り越えるかは、災害時の対応力にも直結します。
さらに、家族や仲間と一緒に行うキャンプでは、役割分担や助け合いの精神も自然と育まれます。これは、避難所生活や地域の助け合いの場でも大きな武器となるでしょう。
実践への第一歩は「知ること」から
もちろん、アウトドア経験があれば万全というわけではありません。
防災は総合的な備えがあってこそ力を発揮します。まずは、自分の住む地域のハザードマップを確認し、どのようなリスクがあるかを知ることから始めましょう。
家具の転倒防止、避難経路の確認、家族との連絡手段など、基本的な備えも忘れずに。
加えて、防災体験施設やワークショップなどに参加し、楽しみながら学ぶ機会を取り入れるのもおすすめです。
楽しみながら備える力を育てよう
自然と向き合うレジャーは、癒しや楽しさを与えてくれると同時に、私たちに“備える力”も授けてくれます。
アウトドアは、防災の訓練そのものです。
「楽しむことが、備えることにつながる」──
そんな視点を、ぜひ次のキャンプや登山に加えてみてください。
その一歩が、大切な人を守る力になるはずです。