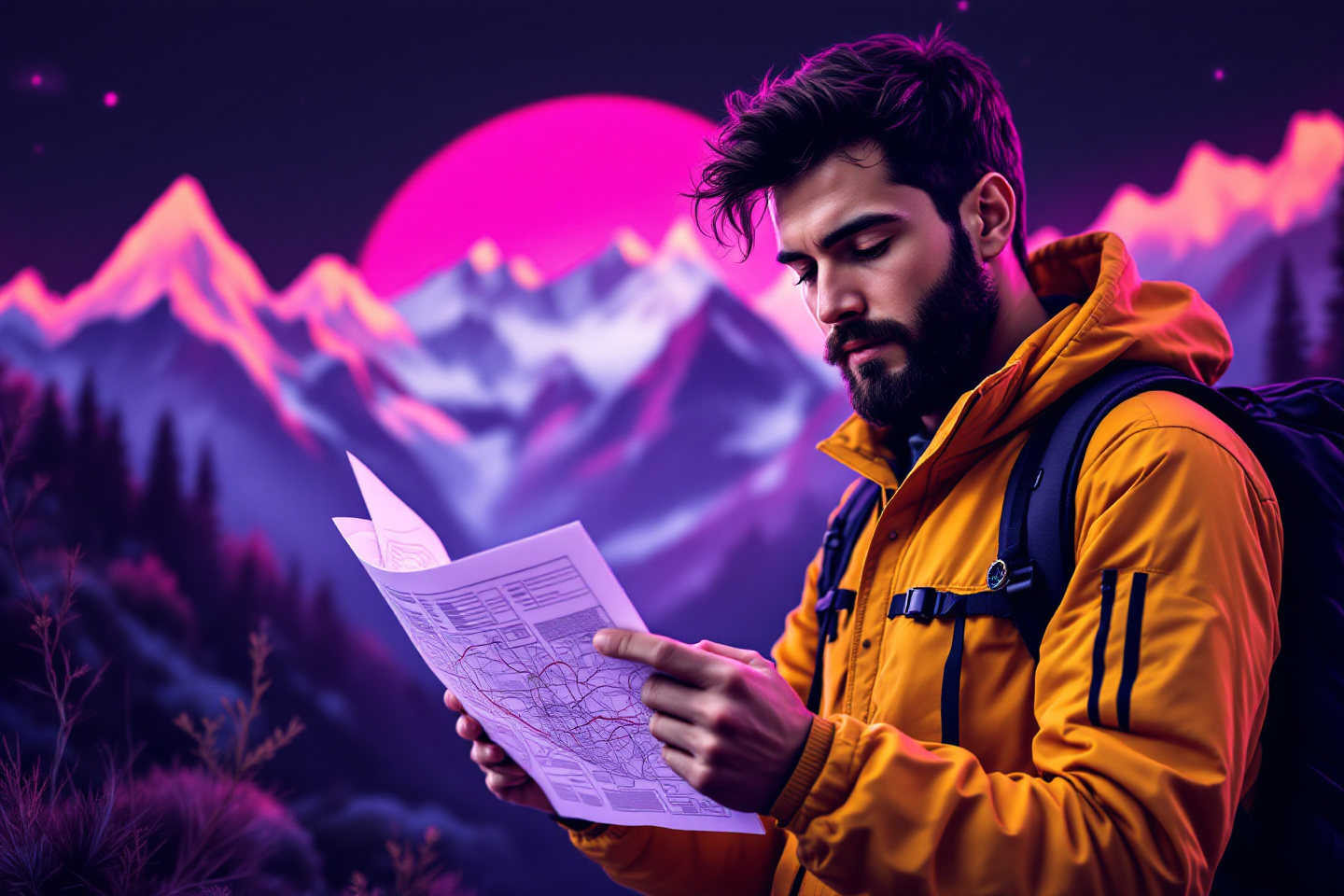自然災害と共に暮らす日本で
日本は、地震・台風・土砂災害といった自然災害が日常と隣り合わせの国です。
山地が多く、川は急流、雨量も多いため、ちょっとしたきっかけで土砂崩れや浸水が起こる地形です。
このような環境で暮らす私たちには、災害に備える意識と行動が欠かせません。
「防災」と聞くと非常食や避難場所の確認を思い浮かべる人も多いかもしれませんが、実はもっと身近な“ある趣味”が、大きな力を発揮することがあります。
それが「ハイキング」です。
ハイキングで培う地形感覚と判断力
ハイキングを通して自然の地形や変化に触れることで、地図を読む力や方角を把握する力が自然と身につきます。
災害時、建物の倒壊や道路の寸断によって避難経路が使えなくなった場合でも、紙地図とコンパスが使えれば、自力で安全なルートを見つけ出すことができます。
また、道に迷った時に引き返す判断や、沢や岩場をどう越えるかといった経験は、災害現場で障害物にどう対応するかにもつながります。
普段から地形を立体的に捉える力を養っておくことで、冠水や土砂災害のリスクが高い場所を見分ける判断にも役立ちます。
非日常における冷静さと行動力
災害時には、誰もが不安やパニックに陥りやすくなります。
自分だけは大丈夫と思い込んだり、周囲の人の行動に流されたりといった心理的な罠も多く潜んでいます。
ハイキングでは、天候の急変やトラブルに対処しながら冷静な判断を求められる場面が多くあります。
例えば、雲の動きから雷の気配を察知して早めに避難する、装備や体力を踏まえて無理のない判断をするなど、自然の中での判断力は災害時にも通用します。
自分で判断し、自分の命を守る行動に移す──
その力は、日常の中ではなかなか得られない経験です。
限られた環境で生き抜く知恵と技術
ハイキングやキャンプを通じて、火を起こす、水を確保する、簡単な調理をするなど、ライフラインが使えない状況下で生き抜くための技術が身につきます。
たとえばメタルマッチなどの着火具に慣れていれば、雨の中でも火を起こせます。
コーヒーフィルターや布を使った水のろ過、煮沸による殺菌といった知識も、飲料水の確保に役立ちます。
ヘッドライト、広口ボトル、タープやシート、携帯トイレなど、アウトドア用品を防災に転用することも可能です。
普段から使い慣れておけば、いざという時にも慌てずに行動できます。
特別な道具でなくても、無印良品やホームセンターで手に入るものを上手に活用する知恵が、防災力をぐっと高めてくれます。
持久力とメンタルの強さも「備え」
災害が起きた後、避難生活が長期化することは珍しくありません。
移動や物資の調達に必要なのは、長時間歩き続ける体力です。
ハイキングで培われる持久力は、避難所までの移動だけでなく、その後の生活を支える力になります。
さらに、自然の中で予想外の事態に立ち向かった経験は、精神的なタフネスを育みます。
疲労、不安、孤立といった避難生活で直面するストレスにも、粘り強く向き合えるようになります。
家族や仲間と協力して登山を乗り越えた経験は、災害時の共助にもつながります。
地域の自主防災組織や近隣住民との連携においても、チームワークや声かけの力は重要です。
日常の楽しみを「防災」につなげよう
ハイキングは、自然を楽しみ、体を動かす気持ちのいい趣味です。
しかし、それだけではなく、私たち自身や家族の命を守るための準備にもなります。
日々の中で自然に身につくスキルや知恵こそが、本当に役立つ「防災力」だと言えるのではないでしょうか。
防災は、何か特別な訓練や知識を持っていなければできないものではありません。
いつもの趣味が、いつか誰かの命を守る力になる。
その視点を持ってハイキングに出かければ、楽しみと備えを同時に手に入れることができるのです。