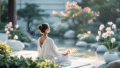不調の原因は見えないところにある?
「なんとなく疲れが取れない」「やる気が出ない」「気分が落ち込みやすい」。
そんな日々の不調を、年齢やストレスのせいだと感じていませんか?
実はその背景に、体の中で静かに働いている“ビタミン不足”があるかもしれません。
目立つ存在ではないけれど、ビタミンは私たちの健康を下支えする「縁の下の力持ち」です。
ビタミンがなければ、エネルギーは生まれない
食事からとった三大栄養素(たんぱく質・脂質・炭水化物)は、体内でエネルギーへと変換されます。
このエネルギーをつくる現場が「ミトコンドリア」。
いわば体内の小さな発電所です。
この発電所を動かすスイッチのような役割を果たしているのがビタミン、特にビタミンB群です。
ビタミンB1やB2、ナイアシンなどは、糖や脂質を効率よく燃やし、エネルギーへと変える代謝の過程に欠かせません。ビタミンが足りないと、栄養をうまく使えず、いくら寝ても疲れが取れない…
そんな状態に陥ることもあります。
心の不調にもビタミンが関係している?
ビタミンは、身体だけでなく“心”の健康にも大きく関わっています。
脳内では、神経伝達物質と呼ばれる化学物質が情報を伝え合い、感情や集中力、睡眠などに影響しています。
たとえば、セロトニンやメラトニン、ドーパミンといった物質の合成にもビタミンB群(特にB6や葉酸)が必要です。
不足すれば、気分が落ち込みやすくなったり、寝つきが悪くなったりすることも。
心のケアと並行して、体の内側=栄養状態にも目を向けることが大切です。
解毒の仕組みもビタミンに支えられている
私たちは、空気中の有害物質や添加物、老廃物などに日々さらされています。
体にはそれを処理する「解毒システム」があり、肝臓が中心的な役割を担っています。
この働きもまた、ビタミンなしではスムーズに進みません。
特にビタミンB群、C、D、葉酸などが、解毒酵素の働きを助けたり、毒性を弱める反応をサポートしたりする役割を持っています。
遺伝的な体質で解毒力が弱い人もいるため、ビタミンのサポートは誰にとっても重要です。
どんな人がビタミン不足になりやすい?
バランスよく食べているつもりでも、ビタミン不足に陥ることは珍しくありません。
加工食品中心の食生活、偏ったダイエット、喫煙や飲酒、薬の使用、胃の不調、ストレス、さらには遺伝的体質などが、吸収や代謝を妨げます。
たとえば胃酸の分泌が弱いと、ビタミンB12が吸収されにくくなります。
また、赤血球の大きさを測るMCVという検査値が高い場合、葉酸やB12不足のサインとされることもあります。
ビタミンをしっかり補うために
ビタミンは、玄米、雑穀、緑の葉野菜、納豆、卵、魚、レバーなどに多く含まれています。
特に水溶性ビタミン(B群やC)は体に溜めておけないため、毎日の食事からこまめに摂ることが必要です。
成長期、妊娠中、高齢者などはビタミンの必要量が増えるため、状況によってはサプリメントの活用も有効です。
ただし、目的に合ったものを選び、摂りすぎには注意しましょう。
体の声に耳を傾けてみよう
倦怠感、気分の変動、肌トラブル、貧血、口内炎などの症状は、ビタミン不足のサインかもしれません。
ただの体質や加齢と見過ごさず、日々の食事や生活習慣を見直すきっかけにしてみてください。
健康という土台を支えているのは、目に見えにくいけれど確かに働いている「ビタミン」。
体の機能を円滑に動かし、本来の元気を取り戻すために、まずは今日の一食から意識を変えてみませんか?