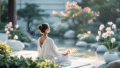避難は「体力勝負」になる
もし明日、大きな地震が起きたら。あなたは子どもと一緒に、徒歩で安全な場所まで避難できますか?
日本は自然災害の多い国です。
地震、台風、豪雨、噴火──いつ何が起きるかわかりません。
災害時には、道が寸断されたり、交通機関が止まったりして、自分の足だけが頼りになる場面もあります。そんな時に問われるのが、「自分の体力」です。
ハイキングが“もしも”に強い理由
日常的に楽しんでいるハイキング。
このレジャーが、実は災害への備えになることをご存じでしょうか?
ハイキングでは、整備されていない山道を長時間歩きます。
坂道、ぬかるみ、岩場などを歩くことで、自然に脚力やバランス感覚、体幹が鍛えられていきます。
さらに、水や装備を詰めたリュックを背負って歩くことは、避難時の荷物運搬の良い練習にもなります。
体が鍛えられるだけではありません。
ハイキング中に天候が急変したり、道に迷ったりといったハプニングに対応する経験は、精神的なタフさも育みます。
判断力や冷静さは、非常時にこそ必要とされる力です。
災害後の「生活」にも体力が必要
避難できたとしても、それで終わりではありません。
被災後の生活には、さらなる体力が求められます。
支援物資を取りに行く、配る。避難所で長時間過ごす。
自宅が無事でも、片付けや清掃などの重労働が待っています。
こうした活動を支えるのもまた、日頃からの体力づくりです。
特に子育て世代や高齢の家族がいる場合、一人で動ける以上の体力が必要になることもあります。
誰かを助けるにも、自分が動けなければ始まりません。
知識や道具は「動ける体」があってこそ活きる
災害時に役立つスキルとして、地図の読み方やコンパスの使い方、火起こし、水のろ過などがあります。
でも、それを実行するには、「行動できる体」があってこそ。
知識があっても、そこまで歩けなければ意味がありません。
道具があっても、使う体力がなければ宝の持ち腐れです。
つまり、体力は他の防災スキルを“実際に活用するための土台”なのです。
無理なく始められる「備え」としてのハイキング
防災というと、堅苦しく感じる人もいるかもしれません。
でも、ハイキングなら楽しく続けられます。
週末に近所の低山を歩いてみる。家族と一緒に自然の中を散策してみる。
そんな軽いスタートでも、確実に体力はついていきます。そして、その積み重ねがいざという時、大切な命を守る力になるのです。
日常が“未来の防災”に変わる
私たちは自然の豊かさと引き換えに、その脅威とも向き合いながら暮らしています。
災害を完全に防ぐことはできませんが、被害を減らす備えはできます。
ハイキングで体を動かし、自然の地形や天候に触れる。心と体を整え、判断力を養う。
こうした日常の活動が、未来の非常時に大きな力となるのです。
「備えること」を重荷にせず、「楽しみながら続けること」こそ、長く続けられる防災のカタチではないでしょうか。