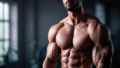不快な症状、その原因は小腸にあるかも?
「最近お腹が張る」「ガスがたまりやすい」「お腹の調子が安定しない」。
そんな違和感を抱えながら、いつものことだと見過ごしていませんか?
その不調、実は「SIBO(小腸内細菌異常増殖症)」という状態が隠れているかもしれません。
SIBOとは、本来は細菌の少ないはずの小腸で、細菌が異常に増えてしまう状態です。
食べたものが小腸で正しく消化・吸収される前に細菌に分解されてしまうため、ガスや腹痛、下痢や便秘など、さまざまな不調を引き起こします。
実際、過敏性腸症候群と診断された人の中にも、SIBOが関係していたという例が少なくありません。
体に起こる変化──単なるお腹の不調ではない
SIBOの症状でよくあるのが「お腹の張り」と「ガス」。
これは、本来は大腸で行われる発酵が小腸で起こることで、通常以上のガスが発生してしまうからです。
ガスは腹痛や膨満感、腸の音などの原因にもなります。
また、細菌が栄養素を消費してしまうため、体に必要なビタミンB12や鉄分が不足しやすくなります。
これが原因で、疲れやすくなったり、集中力が落ちたりすることもあります。
さらに、最近では「腸と脳がつながっている」という“脳腸相関”という考え方も広まっており、SIBOが気分の落ち込みや不安感などの精神面にも影響する可能性があることが分かってきました。
原因はひとつではない──生活習慣や体の変化も関係
SIBOを引き起こす原因はさまざまです。
たとえば、小腸の動きが悪くなると、食べ物や細菌が腸内にとどまりやすくなります。
胃酸が減ることで、体内に入り込む細菌が殺菌されにくくなることもあります。
抗生物質の使用、腸の手術後の癒着、加齢による消化機能の低下、免疫力の低下なども要因として考えられています。
つまり、日常生活の中で誰にでも起こりうる変化が、SIBOの引き金になることがあるのです。
診断と対策──今すぐできることから始めよう
SIBOの診断には「呼気テスト」がよく使われます。
これは専用の糖液を飲んだあと、時間をおいて息を採取し、ガスの成分を測る方法です。
小腸内で異常な発酵があると、呼気中のガスに変化が現れます。
治療の基本は食事の見直しです。腸内で発酵しやすい「フォドマップ」という糖質(小麦製品、玉ねぎ、乳製品など)を減らすことで、症状が軽減されることがあります。
また、消化を助ける酵素や、胃酸の分泌を促すレモン水などを食事に取り入れることも効果的です。
腸内環境を整えるためにプロバイオティクスを使うこともありますが、SIBOのタイプによって合わないものもあるため、自己判断せず専門家のアドバイスを受けるのが安心です。
日常生活では、よく噛んでゆっくり食べること、食事の間隔を4〜5時間あけること、睡眠や運動、ストレスケアを意識することが腸の働きを助けます。
こうした基本的な生活習慣の見直しが、再発予防にもつながります。
腸を整えることは、全身を整えること
SIBOは見逃されやすいですが、慢性的な不調の原因となることも多いトラブルです。
長引くお腹の不快感や体のだるさを「年齢のせい」「体質だから」と片付けず、一度小腸の健康に目を向けてみてください。
腸は「第二の脳」とも呼ばれ、体と心の両方に影響を与える重要な臓器です。
お腹の声に耳を傾けることが、元気な毎日を取り戻すための第一歩になります。