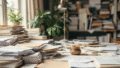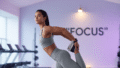最近、なんとなく疲れが取れない、やる気が出ない、頭がぼーっとする…。
そんな不調を感じていませんか?実はそれ、鉄分の不足が関係しているかもしれません。
鉄は、体にとって欠かせない栄養素。
ところが多くの人が、不足していることに気づいていないのです。
鉄分が足りないと、体はどうなる?
鉄は、私たちの体で主に次の3つの働きを担っています。
1つ目は、酸素の運搬。鉄は血液中のヘモグロビンの材料になり、全身の細胞に酸素を届ける役割をしています。
これが足りないと、体全体が酸素不足に。
2つ目は、エネルギーの生成。細胞の中のミトコンドリアが鉄を使ってエネルギーを作ります。
鉄が不足すると、体がエネルギーを生み出せず、だるさや疲れが出てきます。
3つ目は、脳の働きのサポート。鉄は脳内の神経伝達や集中力にも関係しているため、不足すると気分が落ち込んだり、頭が働きにくくなったりすることもあります。
気づきにくい「隠れ貧血」にも注意
「病院の検査で貧血とは言われていないから大丈夫」と思っていても、実は「隠れ貧血」という状態が存在します。
これは、血液中の鉄の貯蔵量(フェリチン)が少ない状態で、ヘモグロビン値は正常でも不調を引き起こします。
とくに、次のような症状が重なっている場合は要注意です。
- 慢性的な疲労や倦怠感
- めまい、立ちくらみ
- 動悸や息切れ
- 爪が割れやすい、顔色が悪い
- 集中力の低下、気分の落ち込み
もし心当たりがあるなら、一度フェリチン値も含めた血液検査を受けてみることをおすすめします。
鉄分には種類があること、知っていますか?
食事から摂る鉄分には、「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」の2種類があります。
- ヘム鉄は、肉や魚などの動物性食品に多く、吸収率が高い(約25%)。
- 非ヘム鉄は、野菜や豆類などの植物性食品に含まれ、吸収率は低め(2~5%)。
この違いを知っておくだけでも、食事の工夫がしやすくなります。
吸収率を上げる食べ合わせ、避けたい組み合わせ
鉄分は、組み合わせ次第で吸収率が大きく変わる栄養素です。
吸収を高めるのは、ビタミンCや動物性タンパク質。
例えば、レモンやキウイ、パプリカ、ブロッコリーといった食材と一緒に、ほうれん草や豆腐を食べると、非ヘム鉄の吸収がぐんと高まります。
逆に、吸収を妨げてしまうのが、カルシウム(乳製品)、フィチン酸(大豆・玄米)、カフェイン(コーヒー・紅茶)などです。
これらは食事の時間とずらすことで、影響を抑えることができます。
サプリメントを使うなら、選び方が大切
食事だけで補いきれない場合は、サプリメントの活用も選択肢の一つです。
ただし、鉄は過剰に摂ると体に負担がかかる栄養素なので、注意が必要です。
おすすめは、胃に優しく吸収されやすい「キレート化鉄(ビスグリシン酸鉄など)」タイプ。
サプリメントを使うときは、表示された摂取量を守り、できれば医師や管理栄養士に相談しましょう。
体も心も元気に動かすカギ、それが鉄分です
鉄分は、酸素、エネルギー、思考力。私たちが「元気でいるための基本」を支えている栄養素です。
特別なことをしなくても、日々の食事や食べ方を少し変えるだけで、鉄分の吸収はぐっと高まります。
慢性的な不調の原因が、もし鉄不足なら、今日からできる工夫で体調が驚くほど変わるかもしれません。
まずは自分の体に目を向けて、できるところから一歩ずつ、始めてみましょう。