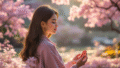その不調、「未病」かもしれません
「なんだか調子が出ない」「肌がかさつく」「疲れやすい」――
そんな漠然とした不調を感じることはありませんか?
病院に行くほどではないけれど、確実に体調がすぐれない。
現代の私たちは、ストレス、情報過多、運動不足、偏った食事など、複合的な要因に囲まれて暮らしています。
東洋医学では、このような状態を「未病(みびょう)」と呼びます。
未病とは、まだ病気と診断されないけれど、健康とは言えないグレーゾーンのこと。
この段階で自分の体の変化に気づき、整えることが、病気を防ぐカギになるのです。
東洋医学が重視する「陰液」とは
東洋医学には、「気・血・水」という三つの要素があります。
このうち「水」の中でも特に重要視されるのが、「陰液(いんえき)」です。
陰液とは、血液、体液、細胞のすき間を満たす液体など、体の内側を潤し、熱を冷まし、臓器や組織の働きを支えるすべての液体のことです。
陰液が不足すると、肌や目、口の乾燥、便秘、不眠、疲労感、イライラなど、さまざまな不調が現れます。
まるで乾いた土がひび割れるように、体が「潤い」を求めている状態です。
特に女性は陰液の消耗に敏感で、年齢とともに減少しやすい傾向もあるといわれています。
陰液を奪う意外な生活習慣
陰液は、知らず知らずのうちに日々の生活習慣によって失われています。
まず注意したいのが、過剰な発汗です。
過度な運動やサウナなどで汗をかきすぎると、体内の潤いが奪われてしまいます。特に、もともと血が不足しがちな体質の人は要注意です。
次に、水分の摂りすぎにも気をつけましょう。
水は生命に欠かせないものですが、必要以上に飲みすぎると、体はそれを排出しようとしてエネルギーやミネラルまで消耗します。
特に年齢を重ねると腎臓の働きが弱まるため、喉が乾いたときに、少しずつ飲むのが理想です。
また、食生活も大きな影響を及ぼします。
小麦製品や乳製品、揚げ物、甘いものの摂りすぎは、腸に「内熱」を生み出し、炎症や陰液の消耗を引き起こす可能性があります。
陰液を守るためにできること
陰液を守るためには、「足す」よりも「引く」視点が大切です。
まずは、小麦や甘いもの、揚げ物など、内熱を生みやすい食品を控えめにするところから始めましょう。
腸内環境を整える発酵食品や食物繊維のある食事も有効です。
水分は、こまめに少しずつ。
体が求めているタイミングで補給し、排泄のリズム(特に便通)を整えることも忘れずに。
そして、質の高い休養が欠かせません。とくに睡眠は、陰液の回復に直結します。
就寝前のスマホ断ちや、寝室の環境整備、毎日同じ時間に眠るなど、ちょっとした工夫が体の修復を促します。
心を整えることも、体を潤す力になる
東洋医学では、体と心は切り離せないものとされています。
特に「肝」は感情のバランスと深く関係し、ストレスによって陰液が消耗されやすくなると考えられています。
すべてのストレスをなくすことはできませんが、「受け流す力」や「自分を癒す習慣」を持つことで、心の潤いは守れます。
深呼吸、瞑想、好きな音楽、自然に触れる時間。
こうした小さな習慣が、内側のバランスを整え、未病の状態から抜け出す助けになります。
体の声に耳を澄ませて、生き生きとした日々を
体はいつも、あなたにメッセージを送っています。
「ちょっと疲れたよ」「潤いが足りないよ」――
その声に、少し立ち止まって耳を傾けてみましょう。
陰液を意識する暮らしは、ただ水を飲むことではありません。
発汗や飲水の量に気を配り、食事や休養を見直し、心を整える。
その積み重ねが、未来のあなたの健康を守り、しなやかな日々を支えてくれます。