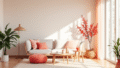「疲れがとれない」「集中できない」「イライラしやすい」──
そんな不調をなんとなく感じながら、毎日をやり過ごしていませんか?
忙しい現代人は、食べる量は足りていても、体が本当に必要とする栄養が不足している「隠れ栄養失調」状態に陥っていることがあります。
今回は、特に不足しやすい栄養素とその対策についてご紹介します。
食べているのに足りていない?栄養の偏りが生む体調不良
私たちの体は、毎日数百グラムのタンパク質を分解し、再合成しています。
筋肉や内臓、肌などの組織が絶えず修復されているからです。
その材料になるのが、食事から摂る栄養素。
しかし、加工食品や偏った食事が続くと、必要な栄養が十分に吸収されず、慢性的な疲労や不調につながることがあります。
特に現代人が不足しやすいのが、ビタミンB群、ミネラル、そしてビタミンDです。
これらは体のエネルギー代謝、神経の安定、免疫の働きに深く関わっており、不足すると心身にさまざまな影響を及ぼします。
不足しやすい栄養素とその影響
ビタミンB群は、食べ物からエネルギーを作り出す際に欠かせない存在です。
例えば、ビタミンB3(ナイアシン)は、疲れにくさや肌の健康に関係しています。
ビタミンB12は赤血球の生成や神経機能の維持に必要で、不足すると貧血や集中力の低下、しびれなどが起こることもあります。
葉酸は遺伝子や神経伝達物質の働きを助け、脳や神経の健康に不可欠です。
ミネラルもまた重要な役割を担っています。
マグネシウムは、エネルギー産生や精神的な安定に関わり、不足すると不眠や不安、だるさを感じやすくなります。
鉄や亜鉛は免疫力や消化機能、脳の働きに関わり、これらの吸収には胃酸が必要です。
しかし、胃薬の常用やストレスによる胃酸の減少が、ミネラル不足を招く原因にもなっています。
ビタミンDは骨の健康だけでなく、気分の安定や免疫機能に関与します。
日光を浴びることで体内で作られますが、屋内で過ごす時間が長くなる冬場は不足しやすく、うつ症状の一因になることも知られています。
吸収を助ける日常習慣とは?
ただ栄養を摂るだけではなく、それを「吸収できる体づくり」も大切です。
まず意識したいのは、胃酸の働き。レモン水や梅干しなどを食事に取り入れると、胃酸の分泌が促され、ビタミンB12やミネラルの吸収が高まります。
食べ物をしっかり噛むことも、消化の第一歩として重要です。
さらに、腸内環境を整えることも忘れてはいけません。
腸は栄養を吸収する場所であり、腸内環境が悪化すると吸収効率も落ちます。
発酵食品や食物繊維を意識して取り入れることで、腸内細菌のバランスが整い、消化吸収がスムーズになります。
また、ビタミンDを補うには、適度な日光浴も効果的です。
特に午前中の太陽を10〜15分浴びるだけでも体内でのビタミンD生成が促進されます。
運動や睡眠も代謝を支える土台となるため、バランスよく取り入れましょう。
生活習慣が栄養不足を招くことも
意外かもしれませんが、日々の生活習慣が栄養の吸収を妨げていることもあります。
加工食品やインスタント食品には、リンや添加物が多く含まれており、体に必要な栄養素の吸収や活性を妨げることがあります。
糖質の過剰摂取も体に負担をかけ、老化の原因となる物質(AGEs)を増やしてしまいます。
また、胃酸を抑える薬の長期使用や極端な菜食主義、アルコール・喫煙といった習慣も、栄養吸収の妨げになる要因です。
こうした生活習慣を見直すことも、栄養バランスを整えるうえで欠かせません。
加工食品を減らすことから始める、隠れ栄養失調対策
完璧な食生活を目指す必要はありません。
まずは「朝食をしっかり噛んで食べる」「日中に日光を浴びる」「加工食品を一つ減らす」といった小さな工夫から始めてみてください。
少しずつでも意識を変えることで、体は確実に応えてくれます。
体に合った栄養素のバランスは人によって異なります。
気になる症状がある方は、医師や栄養士に相談し、必要であれば血液検査などで自分の状態を知ることも大切です。
自分の体と対話しながら、無理なくできる習慣を積み重ねることが、健康へのいちばんの近道です。