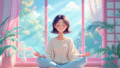水害が多い国・日本の特徴
日本は、四つのプレートがぶつかり合う地形の上にあり、しかも世界有数の多雨国です。
このため、地震や津波に加え、台風や集中豪雨による水害や土砂災害がたびたび発生しています。
近年では、気候変動の影響もあり、これまでの想定を超えるような雨の降り方や災害の規模が増えてきました。
自然の豊かさと引き換えに、私たちは常に災害と隣り合わせに暮らしていることを、改めて意識する必要があります。
大雨・洪水・土砂災害のしくみを知る
集中豪雨の主な原因は、大気中の水蒸気が急速に凝縮してできる積乱雲です。
これが列をなして同じ地域に長時間雨を降らせると、「線状降水帯」と呼ばれる現象となり、大きな被害につながります。
日本の河川は山が多く、海までの距離が短いため、水が急激に流れ下ります。
大雨が降ると川の水位が急上昇し、堤防が壊れたり、水があふれたりすることで、街全体が浸水するケースもあります。
さらに、都市部では、地面が舗装されていて水が地中に染み込まず、排水が追いつかずに道路が冠水する「内水被害」も起こります。
山がちな地形では、雨が地中に染み込み、斜面が突然崩れたり、地面がゆっくり動く地すべり、あるいは土や石が一気に流れ下る土石流など、さまざまな土砂災害も発生します。
これらは一瞬で人命を奪う危険な災害です。
まずは自分の地域を知ることから
水害や土砂災害から命を守るためには、まず自分が住む場所の危険性を知ることが出発点です。
そのために役立つのが「ハザードマップ」です。
自治体が公開しているこれらの地図には、洪水・土砂災害・高潮などの危険箇所や避難場所が分かりやすく示されています。
特に重要なのは、日頃から地図を見て、自宅や職場、学校周辺にどんなリスクがあるかを家族で共有しておくことです。
避難経路も一度実際に歩いてみることで、夜間や雨の日に注意が必要な場所を確認できます。
また、マップで「安全」とされている地域であっても、気象条件次第では被害が及ぶ可能性があることを頭に入れておきましょう。
避難をためらわないために必要なこと
災害時に最も大切なのは、早めの避難です。しかし実際には、避難が遅れて命を落とすケースも多く見られます。これは「正常性バイアス」といって、自分に限っては大丈夫だろうと思い込んでしまう心理が関係しています。また、「周りが逃げていないから」と様子をうかがってしまうことも、避難の遅れにつながります。
実際には、自治体から避難準備の情報が出た段階で、自主的に避難を始めるのが理想です。夜間や風雨が強くなる前に、余裕を持って動きましょう。また、避難するときは、できるだけ徒歩で、家族や近隣と一緒に行動するように心がけてください。車は渋滞や水没のリスクがあるため、なるべく使用しないことが推奨されます。
日頃の備えが生死を分ける
災害への備えは、日常生活の中で無理なく続けられる形が理想です。
食料や水は最低3日分、できれば1週間分を用意しておきましょう。
トイレや衛生用品、照明、充電器、ラジオなどもあわせて準備し、防災リュックにまとめておくと安心です。
中身は定期的に見直し、使ったら補充する「ローリングストック」が効果的です。
また、家具の転倒防止や窓ガラスの飛散防止など、自宅の安全対策も見直しておきましょう。
地域の防災訓練に参加したり、家族で避難先や連絡方法を確認しておくことも大切です。
想定外を想定するという姿勢
私たちの暮らす場所は、自然の恵みと同時にリスクとも隣り合わせです。
「まさかうちが」「こんなに早く」と思ってからでは遅いこともあります。
だからこそ、日頃から「想定外」を想定し、備えることが何よりの防災対策になります。
正しい知識と冷静な判断、そして思いやりのある行動が、家族や地域、そして自分自身を守る力になります。